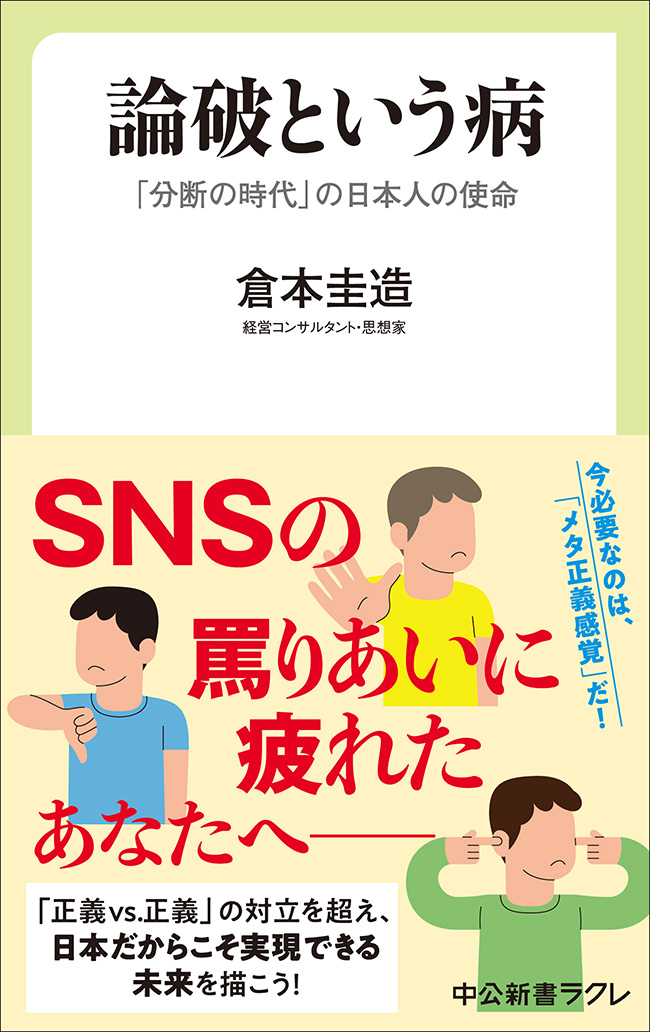著者の倉本圭造さんの経歴がユニークだったために、気になり手に取った本です。
マッキンゼーでキャリアを開始し、その後は肉体労働やブラック企業勤務、カルト宗教団体への潜入、ホストクラブでドンペリを入れもらうなど、様々な経験を経て、船井総研に入社し、現在は独立しているとのことです。
「恵まれたエリート目線では見えないものを知るために(という今思うと少し浅はかな青臭い精神で)」とおっしゃっていましたが、「イシューからはじめよ」でも一次情報に触れることの重要性が語られていたように、素晴らしい姿勢だと思います。
本来であれば、専門性が高いエッセンシャルワーカー(教員や保育士、学校や病院介護施設の調理員など)の待遇はホワイトカラーよりも良くあるべきだと思っており、少し後ろめたい気持ちで日々を過ごしているだけの私とは違います。
本書の冒頭で、「メタ正義感覚」について語られています。
「メタ正義感覚」とは、相手が持つ正義と自分が持つ正義の両方を尊重することです。
足して2で割った妥協案ではなく、相手の意見の存在意義に向き合い、クリエイティブな解決策を考えることが求められます。
これは、メアリー・フォレットが提唱した「統合」に似ていると感じました。
本書には旅行の計画が例として挙げられていましたが、私は注文住宅の設計について考えました。
例えば、「全館空調にしたい」という意見があったとして、その意見の存在意義は「第一種換気を取り入れたい」であったり「室外機の数を減らして外観をスマートにしたい」かもしれません。
後者の理由でかつコストがネックで対立しているのであれば、屋根裏エアコンでも十分に叶えられる可能性があります。
本書では、メタ正義感覚を持つことが、社会課題の解決に向けた重要アプローチであると強調されています。
その後に語られる「水の世界」「油の世界」という概念と、それらを「乳化剤」によって共存させるアプローチ(マヨネーズのような形態)は、まさにメタ正義感覚の実践例として印象的でした。
IT技術の社会実装については、SIerやコンサルタントの立場にある方々がより切実に課題を感じているかもしれません。
著者によれば、日本の働き手は末端まで強い責任感を持ちすぎており、外部からの改善提案を受け入れにくい傾向があるとのこと。
このような状況に対し、著者は「水側の人が油側の人をあと3歩迎えに行く必要がある」と提案しています。
かつては「過剰にカスタマイズを求める人々が合理化を妨げている」という考えを水側の人が一方的に押し付けていましたが、最近は日本企業の事情に歩み寄り、現場のニーズに徹底的に寄り添ったユーザーインターフェースを作り込む企業が増えてきているそうです。
「一つのことをうまくやる」SaaSを組み合わせるUNIX哲学的なアプローチは、特に中堅企業において有効な選択肢になりうると感じました。
著者はまた、「ドラクエ型」と「FPS型」という興味深い概念で日本の競争力低下を説明しています。
ドラクエ型は従来の日本的競争スタイル、FPS型は新しい競争スタイルを表しており、日本が全体的に競争で後れを取っているのは、競争の形態そのものが変化したためだと指摘しています。
ドラクエ型が有効な分野ではまだ強みを発揮できているものの、ソフトウェアや家電といった分野ではFPS型への転換に遅れを取っているとのこと。
これは経営学でいう「知の深化」と「知の探索」の対比に通じるものがあります。自分自身が「ドラクエ型」の思考を持っていたことに気づき、ハッとさせられると同時に、その分析には納得感がありました。
本書は様々な社会課題に対してメタ正義感覚をどう適用していくかを具体的に示しており、読み進めるうちに概念が腹落ちしていく体験ができました。
読後は未来に対してやや希望を持てる気持ちになりました。
課題は山積していますが、議論は既に本書で言う「令和型」に移行しつつあり、地に足のついたメタ正義的な解決策を積み重ねていける兆しが見えると感じました。
本編を通して「〜な意見があり」という形で紹介される多様な意見の存在に新鮮さを覚えました。
これは私自身が似た属性の人々との交流に偏りがちで、著者のように多様な人々と接する機会が少ないからでしょう。
読書を通じて異なる視点や課題を俯瞰し、日本社会の解決策を考える機会を得られることは、ありがたいなあと感じました。
Xでいろんな意見を見ている感覚でいたのですが、実際にはフォローしている人は自分とよく似た属性の人ばかりであることに気づきました。
よく考えたら、フォローしている人以外のつぶやきを見るのは「松村北斗」「内山昂輝」「トンツカタン森本」でパブサするときだけでした。
そのベン図ある?